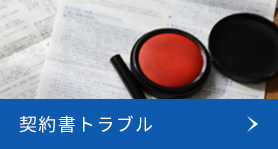古物営業をする上での基本的ルールと実務対応【古物営業法】

はじめに
今回は、古物営業法とは何か、何を守らなければいけないのかを弁護士がわかりやすく解説していきます。
古物営業法とは
|
(目的) 第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。 |
「古物営業法」とは、中古品、リサイクル品などの古物を取引(古物営業)するときのルールなどを定めた法律です。
なぜ、中古品やリサイクル品などの古物の取引についてルールを設ける必要があるのかというと、これらの中には、盗品が紛れ込んでいる可能性があるためです。これを野放しにすれば、犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまうおそれがあります。
そのため、古物営業法は、法令等で定められた各種義務を果たすことにより、窃盗その他の犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復できる社会を維持することを目的としています。
そのために、古物営業を行う主体に対して許可制(古物商、古物市場主)ないし届け出制(古物競りあっせん)として、事業開始にあたっての規制がかかり、かつ、日々の事業を行う上でも、3大義務(後述)をはじめとする義務が課せられています。
古物とは
ここでいう「古物」とは何かを確認していきたいと思います。
「古物」とは、古物営業法第2条1項では、次の3つのいずれかにあたるものと定義されています。
① 一度使用された物品
※「使用」とは、物品をその本来の用法に従って使用すること
(例:衣類→着用、自動車→運行の用に供する、美術品→鑑賞、商品券→交付等して商品の給付等を受ける)
② 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
※「使用のために取引されたもの」とは、自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたもの
※小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、未だ使用されていない物品であっても「古物」に該当
(例:消費者が贈答目的で購入した商品券や食器セットは、「使用のために取引されたもの」に該当)
③ ①・②の物品に幾分の手入れをしたもの
※「幾分の手入れ」とは、物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うこと
(例:絵画→表面を修補、刀→研ぎ直す)
さらに、この「古物」は13品目に分類されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品
- 自動車
- 自動二輪車・原付
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
古物営業とは
では、この古物をどのように取引することが「古物営業」にあたるのでしょうか。古物営業法第2条2項では、以下の3種類に分類しています。
➀ 古物商
└古物の売買等を行う営業です。古物の「売買」「交換」「委託を受けての売買」「委託を受けての交換」を行う営業が可能です。
② 古物市場主
└古物商同士が取引を行う古物市場を経営する営業です。
リサイクルショップの仕入れに利用する古物商同士が取引する古物市場を運営し、参加している古物商から参加料をとったり、取引成立に対する手数料をとったりすることで利益を得るものです。
・古物商でない者から委託を受けた古物商が古物市場で取引することは可能です。
・古物商でない者(海外バイヤー等)が古物市場で取引することはできません。
③ 古物競りあっせん業
└ネットオークションの運営者がこれにあたります。古物を売りたい人、買いたい人(一般人も含む)のあっせんを「競り」によって行い、サービス利用者から利用料をとったり、取引成立に対する手数料をとったりすることで利益を得ます。
*ヤフオクの運営会社等
・古物の「売買を行わない」「売買に関与しない」「売買の場を提供するだけ」
・日本国内に「営業の本拠となる事務所」(法第10条の2第1項)を有する者に限られます。
なお、この3種類の古物営業のいずれかにあたる場合には、古物営業法が定めるルールを守らなければならず、違反するとペナルティを科される可能性があります。
古物商許可が必要なケース
上記のうち、「古物商」や「古物市場主」となる場合には、公安委員会から許可を受ける必要があり(古物営業法第3条)、また、「古物競りあっせん業」をする場合は、営業開始日から2週間以内に、公安委員会に届出が必要になります(古物営業法第10条2)。
では、許可が必要となるケースのうち、古物商のケースを具体的に見ていきましょう。
ネットオークションで中古品を購入したり、自身の不要になったものをフリマサイトで販売したりというように、単発的な取引を行うのであれば古物商許可は必要ありません。
しかし、営利目的で継続して古物の売買を行う場合には、古物商許可が必要となります。
古物商許可の目的は、犯罪の防止と被害の迅速な回復であり、古物商の保護ではないことがポイントです。
今回は、古物商等の許可を得た後に、古物営業をしていく上で理解しておきたいルールについて解説します。
➀ 標識の掲示
古物営業法第12条に規定されているとおり、古物商は営業所・露店において、古物市場主は古物市場において、それぞれ目に付きやすい場所に、標識を掲示しなければなりません。
② 一般的な標識掲示
古物営業法施行規則第11条別記様式第13号に定められているとおり、縦8cm、横16cmの耐久性のある材質で作成した紺色地に白文字の標識を掲示します。記載事項は、許可をした公安委員会の名称、許可番号、取扱い古物の区分、氏名又は名称です。標識は、自分で作成する他、インターネット上のプレート業者や、各都道府県の防犯協会や公安委員会が定めた団体からも購入することができます。
③ ECサイトの場合の標識掲示
ECサイトの場合にも、許可をした公安委員会の名称、許可番号、取扱い古物の区分、氏名又は名称を、サイト上に表示しなければなりません。表示方法は、古物営業を行うサイトの個々のページに表示することが原則ですが、トップページに記載することも可能です。または、当該ページへのリンクをトップページに設置し、古物営業法の規定に基づく表示を行っているページへのリンクである旨を記載します。
④ 管理者の選任
古物商・古物市場主は、古物営業法第13条により、営業所又は古物市場ごとに、その営業所又は古物市場に係る義務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければなりません。 なお、その管理者に対して、取扱い古物が不正品であるかどうかを判断するために必要とされる一定の知識、技能又は経験を得させるよう、努力義務が課されています。特に決まった資格があるわけではありませんが、いわゆる「目利き」ができる専門家として技能向上していくことが求められています。
3大義務
古物商を念頭に置きますと、特に3大義務と呼ばれる以下の義務の遵守が重要です。
- 本人確認義務
- 取引の記録義務
- 不正品の申告義務
以下、具体的に見ていきましょう。
➀ 仕入先等の本人確認
古物営業法は、盗品の流通経路等を捕捉するために、古物商に対して、一定の取引関係がある者については身分確認をしなければならないとしています。
誰の身分を確認しなければならないか?
古物営業法15条第1項において、古物商は、古物の「買い受け・交換」や「売却・交換の委託」を受ける場合には、相手方の真偽を確認する措置をとらなければならないとされています。基本的に「仕入れ」をする場合には、仕入先の身分を確認しなければならないということです。
*身分確認をしなくても良い場合とは
仕入先に支払う代金の総額が1万円未満の場合と、自分で一度売却したものを再度買い受ける場合には、身分確認は不要となります。対価が小さい場合には窃盗対象となる可能性が低いこと、そして、許可を得て、規定を守らなければならない古物商自らが売却した品であれば盗品でない可能性が高いと考えられるからです。
1万円未満でも確認が必要となるケース
代金の総額が1万円未満であっても、下記4つの品物については、一般に盗品が流通するケースが多いため、仕入先の身分確認が必要です。
- 部分品も含めた、自動二輪車、原動機付自転車
- 家庭用コンピュータゲームソフト
- CD・DVD等
- 書籍
*身分確認の方法
身分確認の方法としては、様々な方法が定められていますが、たとえば、下記のような方法があります。大別しますと、対面と非対面があります。かつては対面が主でしたが、情報通信の発達から、非対面の方法が増加してきています。
- 相手の住所、氏名、職業及び年齢を確認する
(自動車運転免許証、被保険者証等の提示を受ける) - 相手から住所等が記載された文書の交付を受ける(面前で署名したものに限る)
- 相手に本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約をする
- 相手から住民票の写し等の送付を受けて、そこに記載された本人名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約をする
- 相手から本人確認書類(運転免許証、国民健康保険者証等)のコピー等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、あわせてそのコピー等に記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金する契約をする
ECサイトで、非対面による身分確認の方法
直接、相手方と会わずに買受け等の古物取引を行う場合には、相手方の身分確認を下記いずれかの方法で行うことが義務とされています。
- 相手方の電子署名入りのメールを受取り、古物の取引を行う
- 古物を受取る際に、相手方から書面に印鑑(会社代表者印)とその印鑑登録証明書を受取る
- 相手方に本人限定受取郵便で書類等を送付して、到着が分かる手段をとる
- 古物の売買代金を本人限定受取郵便にした現金書留で支払う等の取引条件にする
- 住民票の写し(登記事項証明書)の送付を受け、転送しない取扱いで代金を現金書留で支払う
- 住民票の写し(登記事項証明書)の送付を受け、記載された氏名(法人)名義の預金口座に振込む
- 相手方から免許証や保険証のコピーの送付を受け、見積書等を転送しない取扱いで簡易書留にて送付し、相手から了承を得た後に代金を本人名義の口座に振込む
- 上記1~7のいずれかの方法により本人確認をした相手に、ID・パスワードを付与し、これを使い申込みを受付ける
「2回目」以降の取引
同じ相手方との2回目以降の取引では、一度、身分確認が済んでいるため、IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認する措置を既に行っていることを確認できます。例えば、本人確認をした仕入れ先に、第三者に漏れない方法でID、パスワードを付与し、自身のホームページの入力画面から、それを入力してログインでき、申込みを受け付けることができるようにするという方法等がよいでしょう。ただし、記載された顧客情報と2回目以降の申込画面に入力された内容が異なる場合は、再度、身分確認する必要があります。
② 帳簿等への記録義務等
古物営業法は、盗品の流通経路を補捉するために、古物商に対して、取引についての記録義務を定めています。
どのような方法で、どのような場合に記録する義務があるのでしょうか。
記録の方法
帳簿へ記載する、取引伝票の編綴、コンピュータへ入力のいずれかの方法で、以下の5点を記録する必要があります。
- 取引の年月日
- 古物の品目及び数量
- 古物の特徴
- 相手方の住所、氏名、職業及び年齢
- 相手方の身分を確認した方法
記録が必要な取引は?
基本的には、売却を含む古物商の取引すべてに記録義務があるものと規定されています。記録した帳簿は、記録した日から3年間保存しなければなりません。3年以内に記録を紛失した場合は、警察への届け出が必要になります。記録は、紙の保存に限るわけではなく、コンピュータで作成したファイルをハードディスクやその他メモリーに保存したものでも構いません。紙の帳簿は濡れて破れたり、燃えたりすることが考えられますし、ハードディスクは故障することもあるため、どちらにしても何かあった時にすぐに取り出せるようにコピーやバックアップを取っておく必要があります。
仕入れの場合
仕入れの場合は、自分で一度売却したものを買い受ける場合以外のケースで、対価の総額(代金の総額)が1万円以上のものと、対価の総額(代金の総額)が1万円未満の、「バイク、家庭用コンピュータゲームソフト、CD・DVD等、書籍」については、記録義務があります。
売却する場合
売却する場合は、身分確認とは異なり、下記に該当する物品を売却する場合に、記録義務が生じます。記録を取っていなかったということのないように注意が必要です。
- 美術品類
- 時計・宝飾品類
- 自動車(その部分品で1万円以上のものも含む)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(その部分品で1万円以上のものも含む)
③ 不正品の申告義務
古物営業法の目的は、盗品の流通を防ぎ、犯罪の防止と被害の迅速な回復を図ることです。そのため、古物商は、古物の取引をする際に、盗品や偽造品等の不正品の疑いがあるときは、直ちに、警察にその旨を申告しなければならないと、古物営業法第15条第3項に定められています。
以下の場合等が、不正品の疑いがある取引に該当すると考えられます。
- 同一の相手方が短期間のうちに常識外れの多数の物品の売却を繰り返す場合
- 相手方の年齢や職業等に不相応な高額品の売却を行う場合
- 落ち着きがなく売却を急ぎ、売却価格を問わない場合
④ その他の義務
その他、古物商には、以下のような義務も存在します。
許可証の携帯義務
古物商は、行商と呼ばれる、営業所を離れて取引を行う場合やせり売りをする際には、許可証を携帯する義務があります。古物商の代理人、使用人その他従業者についても、行商従業者証というものを携帯させる義務があります。古物商やその代理人や従業員は、行商をする場合において、相手方から許可証等の提示を求められたときは、それを提示する義務があります。
営業の制限
古物営業法第14条第1項により、古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所もしくは居所以外の場所において、買い受け、もしくは交換するため、または、売却もしくは交換の委託を受けるため、古物商以外のものから古物を受け取ってはならないと規定されています。古物商の取引において重点的に規制されているのは、「仕入れ」です。盗品、不正品を仕入れない、仕入れてしまった場合でも仕入れ先を明確に把握するために、このような営業の制限が定められています。また、古物市場においては、古物商間でなければ、古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けることができません。
警察の捜査への協力義務
古物営業法の趣旨に基づき、古物商は「品触れ」(古物営業法第19条)や「差止め」(同第21条)の制度を通じて、警察の捜査に対して協力する義務があります。
品触れ
品触れとは、所轄の警察署が盗品の発見のために、古物商に対して「品触書」といわれる手配書を送付し、被害品の所持の有無の確認と届出を求めるものです。古物商は品触書を受け取った場合、6か月間保存し、該当する古物を所持していたり、保存期間内に受け取ったりしたときは、直ちに警察に届け出なければなりません。
差止め
差止めとは、盗品等の疑いがある古物について、警察が古物商に対して最大30日間の保管命令を行うことです。差し止められた古物は、売却することができず、売買や交換の委託を受けたものを所持していた場合でも、委託者に返却することもできません。
名義貸しの禁止
古物商や古物市場主は、許可制であるため、自己の名義をもって、他人にその古物営業を営ませることができません。つまり、名前だけ貸して他の者に中古品販売等をさせることは禁止されています。
営業内容等の変更に伴う届出
古物商や古物市場主は、営業内容等に変更があった場合、変更日から14日以内(登記事項証明書を添付すべき時は20日以内)に公安委員会に届出書を提出しなければなりません。
まとめ
ここまで、古物営業をする上での基本的なルールについて簡単に解説いたしました。古物商が営業の規制を受ける目的は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図り、窃盗等の犯罪の被害を迅速に回復させることです。そのために、古物商や古物市場主の許可を受けた後にも、古物商を営むために守らなければならないルールが古物営業法に規定されています。スムーズな取引のためにも、上記の内容は理解しておきたいところです。個別のご相談は、随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。